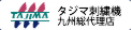技術情報
刺繍糸について

刺繍糸は、基本的に、レーヨン糸が使われております。最近では、ポリエステル糸も増えてきております。
刺繍糸には、太さの単位があります。通常は、120d/2の太さが標準です。最近では、クオリティーアップのために、細めの糸(75d/2)がよく使われるようになってきております。それより細い糸も各糸メーカーからでております。
金糸や銀糸は上記糸と構造が違い、芯糸に金や銀のフィルムを巻き付けた構造になっております。金・銀糸の太さは通常、1掛を使用します。
レーヨン糸の120d/2と太さがだいたい同じです。
クオリティーを上げるためには、8分や5分を利用します。5分がレーヨン糸75d/2相当です。当然、刺繍糸を細くすれば、刺繍データーの糸密度を増やさなければ、スカスカの刺繍になってしまいます。
針について
| 針種 | 番手 | 糸太さ |
|---|---|---|
| K5- | 11 Z1 | 120/2 |
| 1KN- | 11 | 120/2 |
| 9ST- | 11 12 11 |
120/2 120/2 120/2 |
刺繍を自動化した刺繍ミシンの最初が、ジャガード刺繍機です。厚紙でできた帯状の紙に規則的に穴を開けておき、その穴を機械仕掛けで読み取りその情報をキャムを利用して縦と横の動きに変え、ミシンに連動縫いさせる構造。オランダなどにあるオルゴール式のオルガンと、発想が似ています。
はじめは1台のミシンで構成されていましたが、次第に2台、3台と連結して量産が可能になりました。
日本ではタジマ工業(株)が、連結刺繍機を多頭式刺繍機として生産を開始。ワンポイント刺繍ブームがきます。ブームの中、アーノルドパーマーに代表されるような多色刺繍の需要がたかまります。
当初は1色(1針)しかできないため、途中で糸を取り替えて多色の刺繍をしていました。取り替えるのは非効率なので、糸屋に特注で5色を1本の糸に5メートル間隔で染め効率化をはかった業者も現れました。需要にこたえるためタジマ工業(株)は1頭に6本の針を備えた多色機を発売します。
下紙の種類
下に敷く紙は代表的なもので、ハイボンとマツボがあります。
厚さも種類があります。生地にアイロン接着して使用する圧着ノリ付もあります。
刺繍枠選び
刺繍枠は、刺繍の大きさに一番近い枠を使います。
必要以上に大きな枠を使うと、生地のたるみや振動で刺繍に不具合が発生しやすいです。
刺繍方法
通常枠で刺繍
丸枠などで、直接生地を挟み込んで刺繍する。
置き縫い刺繍:下紙利用
下紙のみをはめた枠を刺繍機にセットし、両面テープを張った上から生地をおいて刺繍
置き縫い刺繍:置き縫いシート(ビニール系)
枠にシートをセットし、シートに専用スプレーのりを散布して生地を固定
置き縫い刺繍:パンチシート
シートを枠にセットし、刺繍して、刺繍部分をカッターで切り取り周りに両面テープをはる
置き縫い刺繍:袋物製品など
テーブルが下がる刺繍機でくりぬきステン板に両面テープを張って生地をのせる。
オートクランプ枠
厚手の素材など枠にはまらないものなどを2枚の板で挟み込む。エアーを使い自動で開閉できる。
簡易クランプ枠
オートクランプの小型版で挟み込みをローレットで締めこむ
手法あれこれ
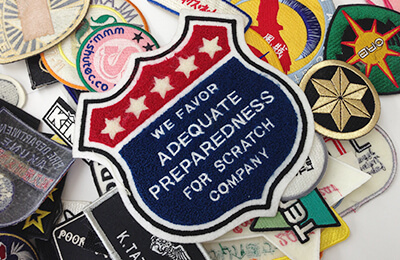
簡易クランプ枠
ウレタンフォームを一緒に縫込み余分をとりさります。
鹿の子のポロシャツにきれいに刺繍
刺繍する面にハイセロンフィルム(薄手の水溶性)を載せて刺繍します。
メッシュの生地に刺繍
エンビフィルムを刺繍する面に置いて刺繍(刺繍密度を高めにする必要あり)
切れ端の生地などぎりぎりに刺繍
生地にのり付ハイボン(紙)を大きめに熱圧着して枠にはめる。
アップリケ刺繍
刺繍データーでアップリケする生地のカットデータを作成カットして、そのデーターをベースにアップリケデーターを作成
針の交換基準

- 糸の太さがかわる場合(120d/2⇔75d/2、または金銀糸の番手変更)
- 刺繍する生地が変わる場合(ニット生地・本皮・新合繊など)
- 針先が折れている場合
- 針が曲がっている場合
- 針穴にのりなどの異物が付着した場合など。
ボビン・ボビンケースについて

必ず、ボビンはタジマ指定のアルミボビンを使用してください。 ボビンケースは、刺繍の糸調子に関わる重要な部分です。ブタのシッポの部分や糸押さえ部分が痛んだら、即交換してください。 基本的には、ボビンケースは消耗品ですので、定期的に交換してください。
 野中ししゅう機販売株式会社
野中ししゅう機販売株式会社